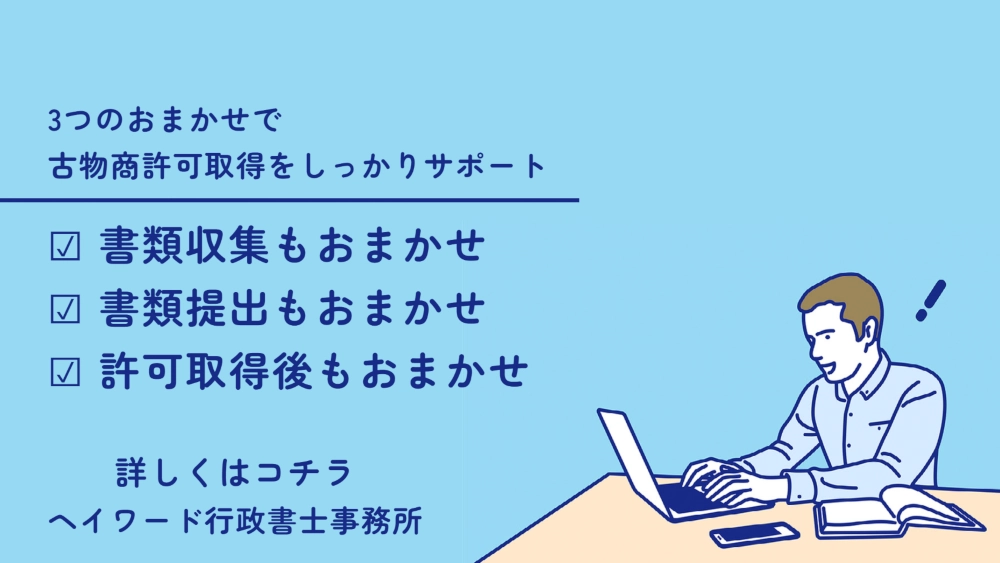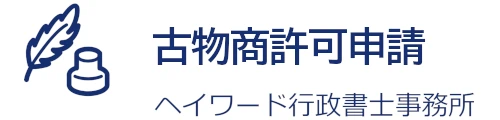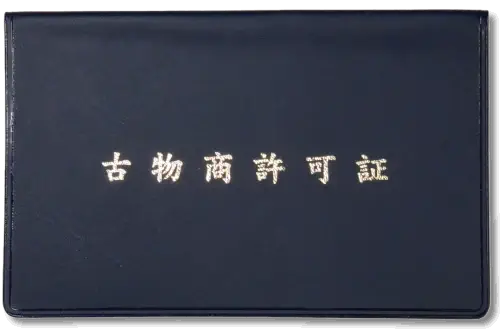古物商許可申請の必要書類一覧と取得方法を解説【個人・法人】

はじめに
古物商許可を取得するためには、許可申請書のほか、さまざまな書類を揃えて申請する必要があります。書類に不足があると申請を受理してもらえないため、正確に準備することが重要です。
本記事では、個人申請と法人申請における必要書類を一覧で整理し、公的証明書の取得方法や書類作成時の注意点について、行政書士が詳しく解説します。
目次
必要書類一覧(個人・法人)
個人申請と法人申請における必要書類の一覧は以下の通りです。
なお、個人申請者または法人の役員が管理者を兼務する場合、住民票、身分証明書、略歴書は各1通の提出で問題ありません。ただし、誓約書については、個人用または法人の役員用に加え、管理者用の書面も提出する必要があります。
| 個人申請 | 法人申請 | |
|---|---|---|
| 1. 許可申請書 | 必要 | 必要 |
| 2. 住民票 | 申請者・管理者 | 全役員・管理者 |
| 3. 身分証明書 | 申請者・管理者 | 全役員・管理者 |
| 4. 略歴書 | 申請者・管理者 | 全役員・管理者 |
| 5. 誓約書 | 申請者・管理者 | 全役員・管理者 |
| 6. 定款の写し | 不要 | 必要 |
| 7. 登記事項証明書 | 不要 | 必要 |
| 8. URL疎明資料 | インターネットを利用する場合 | インターネットを利用する場合 |
| 9. 営業所の使用承諾書など | 管轄警察署による | 管轄警察署による |
古物商許可申請における住民票など公的証明書の有効期限は、交付日から3か月となっています。
忙しい方は行政書士にお任せするのがおすすめです
古物商の許可申請を行うには、このように多くの書類を揃える必要があります。特に、仕事や家庭の事情で忙しい方にとっては、申請手続きを自分で進めるのは大変な作業です。
そんなときは、専門家である行政書士に依頼することを検討してみてください。行政書士は、必要書類の収集から申請書の作成、提出までのプロセスをサポートし、申請の成功率を高めることができます。これにより、時間と労力を節約し、安心して申請手続きを進めることができます。
1. 許可申請書
古物商の許可申請書は、各都道府県警察本部のホームページからダウンロードできます。申請書には、定められた様式に従って申請者の情報(氏名・名称や住所など)や取り扱う古物の区分などを記載する必要があります。
営業所の数や法人役員の数に応じて、追加書類が必要となる場合がありますが、以下の3つの書類は個人・法人を問わず必ず提出しなければなりません。
- 別記様式第1号その1(ア)
- 別記様式第1号その2
- 別記様式第1号その4
2. 住民票の写し
住民票の写しは、「本籍」の記載があるものが必要です。請求は「世帯の一部」とし、「個人番号(マイナンバー)」や「世帯主との続柄」の記載がないものを選択してください。
なお、「マイナンバー」と「世帯主との続柄」は、申請しない限り記載されませんので、申請時には「本籍」にのみチェックが入っていることを確認しましょう。特に、マイナンバーが記載されている場合、警察署で受理されないことがありますので注意が必要です。
外国籍の方は「国籍・地域」「在留資格」「在留カード等の番号」「通称(ある場合)」の記載のある住民票を取得してください。また、許可申請時に「在留カードのコピー(表裏)」を提出するとスムーズに手続きが行えます。
住民票の写しの請求方法
住民票の請求先は、現在住んでいる住所地の市役所、区役所、または町村役場です。
また、マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニでも取得できます(紙製のマイナンバー通知カードでは取得できません)。
POINT - 住民票の写し
請求方法
- 「本籍」を記載する
- 「世帯の一部」で請求
記載不要
- マイナンバー
- 世帯主との続柄
例えば、代表取締役が夫で、取締役が妻である場合、夫が「世帯の全部」で請求した住民票では、妻の住民票を兼ねることはできません。それぞれの住民票は、各人が「世帯の一部」として取得するようにしてください。
3. 身分証明書(≠運転免許証)
身分証明書とは、運転免許証やパスポートなどのことではなく、本籍地の市区町村が発行する「破産の有無」や「成年後見の有無」などを証明するものです。
これは、古物商(個人・法人役員)と管理者の欠格事由のひとつである「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者ではない」ことを証明するために必要な書類となります。
外国籍の方は、本籍がありませんので「身分証明書」の提出は不要です。
身分証明書の請求方法
身分証明書の請求先は、「本籍地」の市役所、区役所、または町村役場の戸籍課となります。また、住民票とは異なり、マイナンバーカードを利用したコンビニ発行には対応していません。
したがって、例えば、住所地が東京都中央区であっても本籍地が文京区であるならば、住民票とは別に請求しなくてはならず少し手間がかかることになります。なお、請求には「筆頭者氏名(市区町村によっては生年月日も)」の記入が必要です。
POINT - 身分証明書
- 運転免許証などのことではない
- 請求先は「住所地」ではなく「本籍地」の市役所等
- コンビニでは発行できない
住民票と身分証明書は郵送で請求できる
住民票と身分証明書は、わざわざ市役所等に出向くことなく、郵送でも請求することができます。各市区町村役場によって若干異なることもありますが、概ね、以下のものを指定の受付窓口に郵送して請求します。
- 各市区町村が用意する「住民票又は身分証明書交付請求書」
- 返信用封筒(請求者の氏名・住所を記載し、切手を貼付)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなどのコピー)
- 手数料(平均各300円)
手数料の納付は郵便定額小為替
手数料は、多くの市区町村で郵便定額小為替を同封して納付することとなっています。郵便定額小為替は、ゆうちょ銀行又は郵便局の窓口で購入することができます。
選べる額面は、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類ですが、発行手数料が各200円かかります。
例えば、住民票及び身分証明書の請求のために、定額小為替を2枚購入して300円×2=600円支払った場合、定額小為替の発行手数料については、200円×2=400円かかることになります。

古物商の許可申請書の
作成はもちろん
住民票や身分証明書の
取得もおまかせ
\ 古物営業ガイドと古物台帳を無料提供中 /
ヘイワード行政書士事務所
4. 略歴書
直近5年間の職歴や学歴などの経歴を記載する必要があります。職歴の場合は「平成〇年〇月 株式会社○○ 入社」、学歴の場合は「平成○○年○月 ○○大学○○学部入学」というように記載します。ポイントは、「空白期間がないように記載」することです。
仮に無職の期間があった場合でも、「無職(就職活動のため)」「無職(親の介護のため)」などと記載し、直近5年間を抜けがないようしっかり埋めましょう。
なお、住所に関しては、住民票または登記事項証明書の表記の通り(1丁目1番-1など)に記載してください。
| 年 月 | 経 歴 内 容 |
|---|---|
| 平成○年○月 | 株式会社○○ 入社 |
| 令和○年○月 | 株式会社○○ 退社 |
| 令和〇年○月 | 株式会社□□ 入社 |
| 令和〇年○月 | 株式会社□□ 代表取締役就任 現在に至る |
略歴書のダウンロード(DOC / 警視庁)
他県の様式と異なる場合がありますので、申請先の県警が用意する略歴書を使用することをお勧めします。
例:愛知県警では「職歴」に加えて「住所歴」の記載も必要である一方、千葉県警では既定の様式がありません。
5. 誓約書
誓約書では、個人申請者、法人の役員、管理者の三者について、欠格事由(許可を受けられない理由)に該当していないことを確認します。
欠格事由はそれぞれ異なりますので「個人用」「法人の役員用」「営業所の管理者用」の3つの様式が用意されています。用紙左上の記載を確認して、取り違えないように気を付けましょう。
住所に関しては、略歴書と同様に、住民票または登記事項証明書の表記の通り(1丁目1番-1など)に記載してください。
誓約書のダウンロード(PDF / 警視庁)
他県の様式と異なる場合がありますので、申請先の県警が用意する誓約書を使用することをお勧めします。また「誓約」するものなので、PCなどで書類を作成する場合でも、氏名は自署(直筆)するようにしてください。
例:管理者の誓約書において、警視庁では「営業所」の住所(及び営業所名)を記載するのに対し、他の道府県警察では概ね「管理者」の住所を記載します。
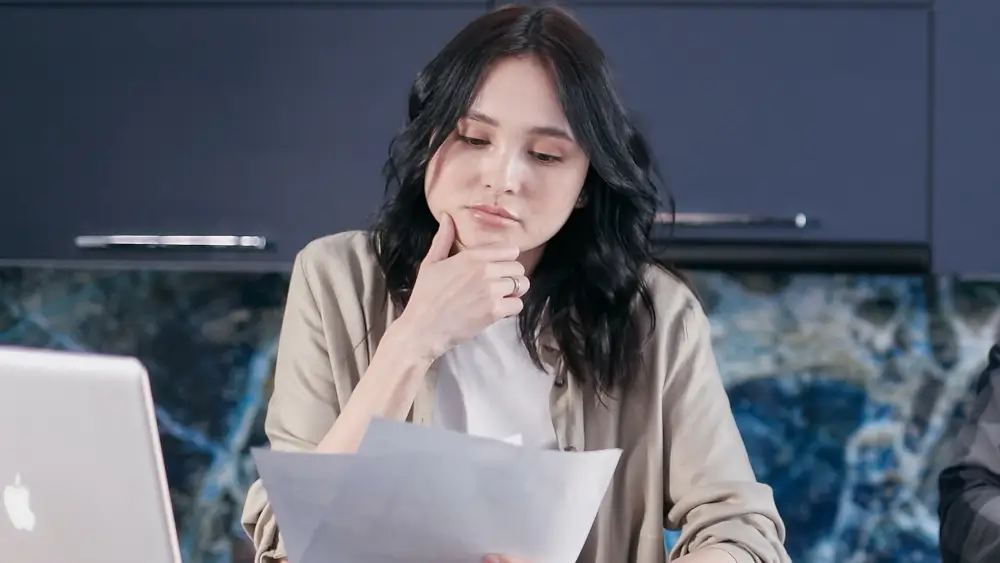
https://hayward-law.com/kobutsusho/古物商許可/サポート
【丸投げサポート】すぐに古物商の許可が欲しいけど、何をしたらいいかわからない方におすすめ。
【東京・千葉・神奈川・埼玉限定】忙しい平日の日中に、申請代行も受付中。個人・法人どなたでも対応OK。
※神奈川・埼玉は一部の地域
6. 定款の写し(法人の場合)
申請者が法人の場合、現行定款のコピーを提出する必要があります。原本ではなくコピーでの提出となるため、そのコピーには、原本と相違ないことを証明する奥書を付ける必要があります。
奥書の方法としては、コピーした定款の最終ページの余白に、余白がない場合は白紙のページを追加して、以下のような証明文を記載し、代表者印を押印します。定款が複数ページにわたる場合は、左側を二か所ホチキスで留めてまとめてください。
以上、原本と相違ないことを証明する
令和○○年○○月○○日
東京都中央区京橋〇丁目〇-〇
株式会社○○○○
代表取締役 ○○○○ ㊞
割印と朱書き
都道府県によっては、会社代表者印による各ページへの割印や、朱書き(赤文字)での記載が必要になる場合がありますので、事前に確認しておくことをお勧めします。
定款は、コピーしたものに毎葉割印のうえ末尾に「以上、原本と相違ありません。」の奥書、コピーを作成した日付、代表者の役職と氏名を朱書きし、代表者印を押印したものを提出してください。
京都府警 - 古物商・古物市場を営むには
7. 登記事項証明書(法人の場合)
登記事項証明書には4種類ありますが、古物商許可申請に必要となるのは「履歴事項全部証明書」です。
なお、管轄警察署によっては、事業目的に「古物営業を営む旨」の記載がない場合、申請が受理されないこともありますので、事前に確認することをお勧めします。
登記事項証明書の請求方法
登記事項証明書の請求方法としては、以下の3つの方法があります。
- 法務局や登記所の窓口で直接請求
- 郵送請求
- オンライン請求
急いでいる場合は、登記所等に直接出向いて請求した方が早いでしょう。手数料は、以下の通りです。
- 書面請求(窓口請求・郵送請求)… 600円
- オンラインで請求して、登記所等の窓口で交付を受ける場合 …
480円→490円 - オンラインで請求して、郵送してもらう場合 …
500円→520円
※令和7年4月1日より「オンライン請求郵送受取」と「オンライン請求窓口受取」の手数料が改定(値上げ)されました。
8. 自社のホームページやフリマアプリなどを利用する場合
自社のホームページやフリマアプリ、AmazonなどのECサイトを利用して古物の取引を行う場合、そのURLを申請書(別記様式第1号その4)に記載して申請する必要があります。
令和7年10月22日のメルカリ利用規約の改定により、事業者(古物商など)のメルカリへの登録および利用が禁止されました。
参考:フリマアプリ「メルカリ」への法人・個人事業主による登録は禁止を明確化。今後も利用するには?メルカリShopsについても解説 | メルカリ Column(コラム)
URLの使用権限を疎明する資料
インターネットを利用する場合、そのURLを使用する権限があることを疎明する資料を添付書類として提出しなければなりません。疎明資料としては、以下のようなものがあげられます。
- 自社のホームページなどの場合:「WHOIS検索」の検索結果をプリントアウトしたもの
- フリマアプリの場合:ショップのプロフィールページをプリントアウトしたもの など
9. 管轄警察署による場合(営業所の使用承諾書など)
申請する都道府県や管轄警察署によっては、上記書類に加えて、営業所に関する以下の書類の提出が求められる場合があります。
特に、自宅を営業所とする場合、自宅が賃貸や集合住宅であれば、大家さんや管理会社から古物商の営業所として使用する承諾を得るのが難しいことがあります。これは許可の適否に大きく関わるため、必ず事前に確認してください。
- 営業所とする物件の所有者の使用承諾書
- 土地・建物登記簿謄本の写し
- 賃貸借契約書のコピー
- 周辺図
- 内部平面図 など
宮城県警のある警察署では、営業所の使用承諾書を「同意書」と呼んでおり、同意が得られない場合には、将来、物件の所有者との間で生じるトラブルに関して一切の責任を負う旨の「誓約書」を提出することが求められます。